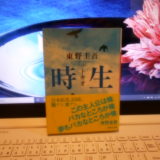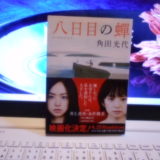こんにちは。
はるき ゆかです。
私が子供の頃、何かほしいものがあったら、祖父や祖母におねだりしていた記憶があります。
おじいちゃんやおばあちゃんは、「お金持ち」だと思っていたからです。
それが、今、崩壊しようとしています。
下流老人は特別な人のことではない
現役世代の年収が400万円以上である人でも、高齢者になると「下流」になるリスクが高いと言います。
本書で言う「下流老人」とは
生活保護基準相当で暮らす高齢者およびその恐れがある高齢者と定義する(本文より)
のことです。
私の亡くなった父は、ある程度の貯蓄はありましたが、貯蓄を取り崩すことなく年金だけで生活できていたと思います。
しかし、それは70代前半でなくなっているからだったようです。
平均寿命が延びている今、100歳まで生きる方も多い。
そのため、現在の現役世代が年金を受け取るときの参考にはならないようです。
私たちの世代は下流老人になる可能性が高い
私たちの世代は、非正規雇用の人が昔に比べて多いのは誰もが知るところです。
非正規でも、長期の派遣社員や契約社員なら、社会保険に加入することは出来ます。
しかし、正規雇用の人に比べると、元の収入の差があるため、厚生年金保険料も少ない。
そのため、受け取る年金自体が少なくなるのです。
私たちの世代は、「下流老人」となる人が多くなるのは、目に見えています。
今から、出来るだけ貯蓄することが大切です。
本書で紹介されているある高齢者は、正規雇用で退職金などもあり、3000万円の貯蓄があっても、生活の仕方によっては「下流老人」となった人もいるようです。
それは、生活水準を現役世代のときと変えられなかった場合です。
また、高額療養費制度など、国の扶助制度を知ることも必要です。
国は取る方には積極的ですが、国民なら受けることができるはずの制度を積極的に教えてはくれません。
そのため、自ら知っておく必要があります。
年金生活に入る前に、ある程度、自分の生活を顧みることと、様々な制度について知っておく必要がありそうです。
一部の富裕層以外は、何もしなくても豊かな老後を送ることは、もう望めないのです。
身体が元気であれば、働くことも出来ます。
それは、元気な今だからそう感じることであって、ほとんどの人は高齢になるにしたがって、どこか体に不具合が出てくるものだと思います。
「年金が少ないのであれば、働けばいい」というのも、誰もが出来ることではないようです。
生活保護は恥ずかしいことではない
本書では、生活保護を受給することを恥ずかしいことと考えないことが大切だと言われています。
不正受給は、もちろん絶対にしてはいけませんが、どうしても生活が苦しく最低限の生活が出来なくなったら、受給すべきだとのことです。
それは、国民に与えられた権利で、恥ずかしいことだと考える必要はないということです。
生活保護のイメージが悪いのは、充分な金額を受給しているのに足りないと言う人がいたり、不正受給をする人があとを絶たないからだと思います。
また、生活保護は、貧困ビジネスに利用されてしまうことも。
しかし、「下流老人」になっても、楽しい老後を過ごしている人はいます。
本書では、大切なことは人間関係だと言われています。
家族がいない人は、地域のコミュニティなどに参加し、一人にならないこと。
人と関わることは煩わしいことも多いですが、特に一人暮らしの高齢者は話し相手が必要です。
人と関わっていれば、悲しい最期を一人で迎えることもないのです。
私個人の思い
本書は、現在、一人暮らしで、両親の介護のため非正規雇用の期間が長かった私にとっては、かなり衝撃的でした。
私には、兄がいますが、兄に頼ることは考えたことはありません(本書ではそれがよくないと言われていますが)。
今は人並みに友人もいますし、孤独になってしまうことはないと思いますが、孤独死に関しては、今からとても心配しています。
持病もありますし、身体も丈夫な方ではないので…。
私は、ずっと前から考えていることがあります。
厭世的になっているわけでも、悲観的な思いがあるわけでもなく、「安楽死」を合法化してほしいと思っています。
本書では、断固として「失われてもいい命はない」と書かれています。
「生活保護を受けなければ生活できないなら安楽死しろ」という人もいるそうですが、そういうことではないのです。
事前にカウンセリングなども必要だとは思いますが、自ら安楽死を望んだ人にはそれを認めてほしい。
自然に亡くなるまでは、生きることを望む人にまで強要することではありません。
私は、もっと前向きに安楽死をとらえています。
もちろん、病院で看取ってもらうことがベストだとは思いますが、それが出来なかった場合、残された親類にどれだけの迷惑をかけるのかと考えると、孤独死すること自体より気が滅入ります。
自分の最期は、自分で選択したいのです。
これは、本書の趣旨とは異なりますし、本書の中では安楽死をすすめるようなことは一切書かれていません。
あくまでも、本書を読んで、改めて私個人が思いを強くしたということです。
私には、子供はいませんし、ただ命を維持するだけになってしまったら、ぜひ安楽死を選択させていただきたいと思います。
実際に、私達が高齢者になる頃には、安楽死の合法化が現実化しているのではないかと思っています。
少子高齢化が叫ばれて久しい。
若者が、結婚して子供を生み育てるためにも、負担をかけたくないと思います。
希望者にはぜひ、安楽死を。
最後に
藤田孝典著「下流老人 一億総老後崩壊の衝撃」の感想でした。
著者の意図するものとは違う感想になってしまいましたが、私にとっては、かねてから考えていた安楽死について、さらに強く希望する結果となりました。
いろいろな考えがあってよいと思います。
ひとつの考え方として捉えていただければと思います。
私は、決して人生を悲観しているわけではありませんし、働けるうちは働きたいと思っています。
こんなことを言っていても、元気で100歳まで生きている可能性もあるかもしれません。